【経営コンサル】問題解決フレームワーク
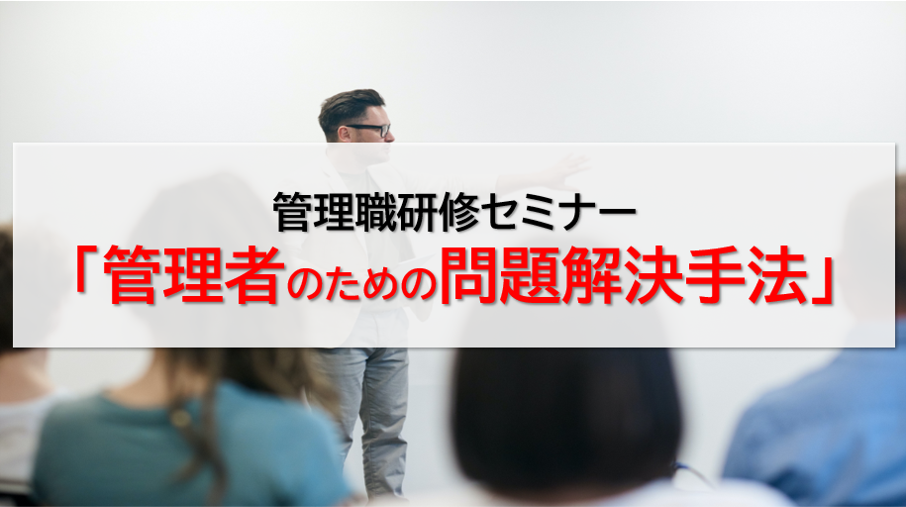
こんにちは、中小企業診断士の諸岡です。
先日、某企業様にて「管理者のための問題解決力」というテーマで6時間研修の講師として登壇させて頂きました。
「問題」というものはそもそもどういう定義なのか、真因を突き止めるための思考法、そして解決策を考えるプロセスについて演習を踏まえて実践頂いた研修でした。
リスキリングが叫ばれる昨今、このような論理的思考力は非常に重要な要素であると考えます。
「問題」とは
そもそも「問題」とはビジネス上どのように定義づけされるのでしょうか。
今回の研修では、以下のように定義づけさせて頂きました。
「問題とは、目標と現状とのギャップであり、解決すべき事柄である」
つまり、目標が高ければ現状とのギャップは大きくなりますし、目標がなければ現状維持ということで、そのギャップはなく、「問題はない」ということになります。
また、よく混同しがちですが、「問題」とは上記の定義であり、「課題」とは「問題を解決するためにやるべきこと」と定義されます。
即ち、「問題」=「What」(起きている事情)、「課題」=「What to do」(やるべきこと)なわけです。
まず「問題」というものを解決するためには、「目標」をしっかり固める必要性があるということです。
「なぜなぜ分析」
トヨタ自動車のカイゼン手法として「なぜなぜ分析」というものがあります。
問題が明確に定義された後には、その問題の要因は何なのか?を突き止める必要性があります。
例えば、次のような事例があったとします。
【目標】 週末に妻と二人っきりで久しぶりに温泉でのんびりすごしたい。
【現状】 仕事がたてこんでいて、週末までに仕事が終わらない。
【目標と現状のギャップ(=問題)】 平日に仕事を終えることができない。
上記で問題が「平日に仕事を終えることができない」ということが明確になりました。
ここから「なぜなぜ分析」です。
なぜなぜ分析は、「なぜ?」を5回繰り返すという手法です。
【目標と現状のギャップ(=問題)】 平日に仕事を終えることができない。
【なぜ?①】 1日あたりの業務量が多くてさばききれていないから。
【なぜ?②】 指示された仕事を指示された順番にやっているから。
【なぜ?③】 上司が「この仕事が最優先だ」と全て言ってくるから。
【なぜ?④】 すべての仕事が「緊急案件」と捉えているから。
【なぜ?⑤】 緊急な事態に気が付くまで放置しているから。
ここまで掘り下げると、「緊急案件に追われない仕組みが必要である」ということが見えてきますね。
そうすると、ミーティングなどで「危険予測を考える」なども解決策の一つになるかもしれませんし、「業務の優先順位の付け方を考える」もその一つになるかもしれません。
もし、これが「なぜ?①」で止まってしまうと、解決策は「1日あたりの業務量を減らす」という表面的な解決策になってしまい、結果根本的な部分は解決していないということになります。
問題を繰り返さないためには、真の要因となる「本質」を理解する必要があります。
したがって、「なぜ」は5回繰り返すと良いと言われます。
ブレスト
問題の真因にたどり着いたら、次に考えるのは解決策です。
解決策は複数用意することが重要です。
そして、一人の凝り固まった志向の中で考えてしまうと、柔軟な発想に乏しくなってしまいます。
そこで活用されるのが「ブレスト」。
ブレストとは、ブレーンストーミングの略で、複数の人たちで集まって自由滑沢に意見を出し合う手法です。
その問題に対して解決策は決して一つではありませんので、皆で自由に意見を出し合ってその解決策を考える手法です。
ブレストには以下のルールがあります。
① 質より量にこだわる。
② 他人の意見の否定は禁止。
③ 他人の意見を膨らませる。
④ 途中で結論を決めつけない。
⑤ 本質を見失わない。
大事なのは、やはり「質より量にこだわること」と「他人の意見を否定しないこと」です。
「知恵」というものは、一人では限界を迎えやすくなりますが、複数の人間が集まることで次なる発想やアイデアが生まれやすくなります。
収束
ブレストで意見を出し尽くしたら、次は何かしらの枠組みで意見を収束していくプロセスです。
似通った意見も豊富に出てくることも当然ありますので、何かしらのタイトルをつけてその枠に集約させていくのです。
そうすると、出し尽くしてきた意見がそれなりにまとまっていくことが分かると思います。
優先度マトリクス
最後に活用するのが「優先度マトリクス」というものです。
2軸を用いて、例えば縦軸は「効果」、横軸は「コスト」のようにマトリクスを作って、先ほどの収束した意見を何かしらの判断軸でプロットしていきます。
プロットしたら、最後に「長期的視点ではこれ」や「効果を優先するのでこれ」といったように、何かしらの判断軸をもとに解決策に優先度をつけていくというやり方です。
解決策を考える際には、「なぜその解決策を選んだのか?」という根拠がある方が説得力も納得性も高いでしょう。
ここまでのプロセスをしっかり経ていれば、解決策の効果の精度は高いものとなるでしょう。
マネジメント研修を楽しく!
昨今、「マネジメント研修」というものが実施されるケースが増えてきています。
マネジメント研修の中でも「問題解決志向」に関する研修は非常に人気があります。
今回の研修でもそうですが、私は「演習」「ケーススタディ」というものをふんだんに含めて、楽しく手を動かし、参加者同士がわいわい言いながら進める研修を意識しています。
特に「問題解決志向」と言う言葉だけを聞くと、やや難しくとらえられがちです。
今回の研修も、いかに楽しく、いかに笑いあり、動きあり、そして学びあり、という研修をプロデュースすることを意識して準備しました。
楽しく和気あいあいな企業研修をプロデュースしております!
企業研修のご相談は気軽にお問い合わせください。
ご興味ある方は是非こちらをクリック!
